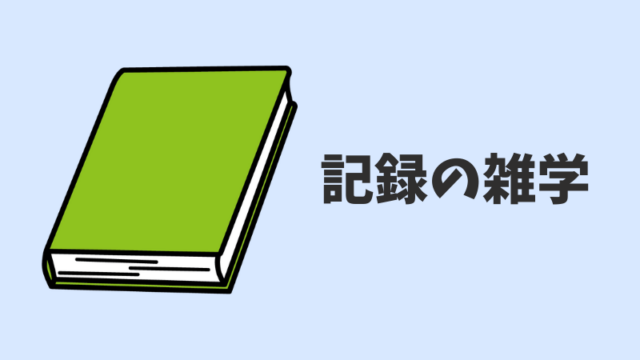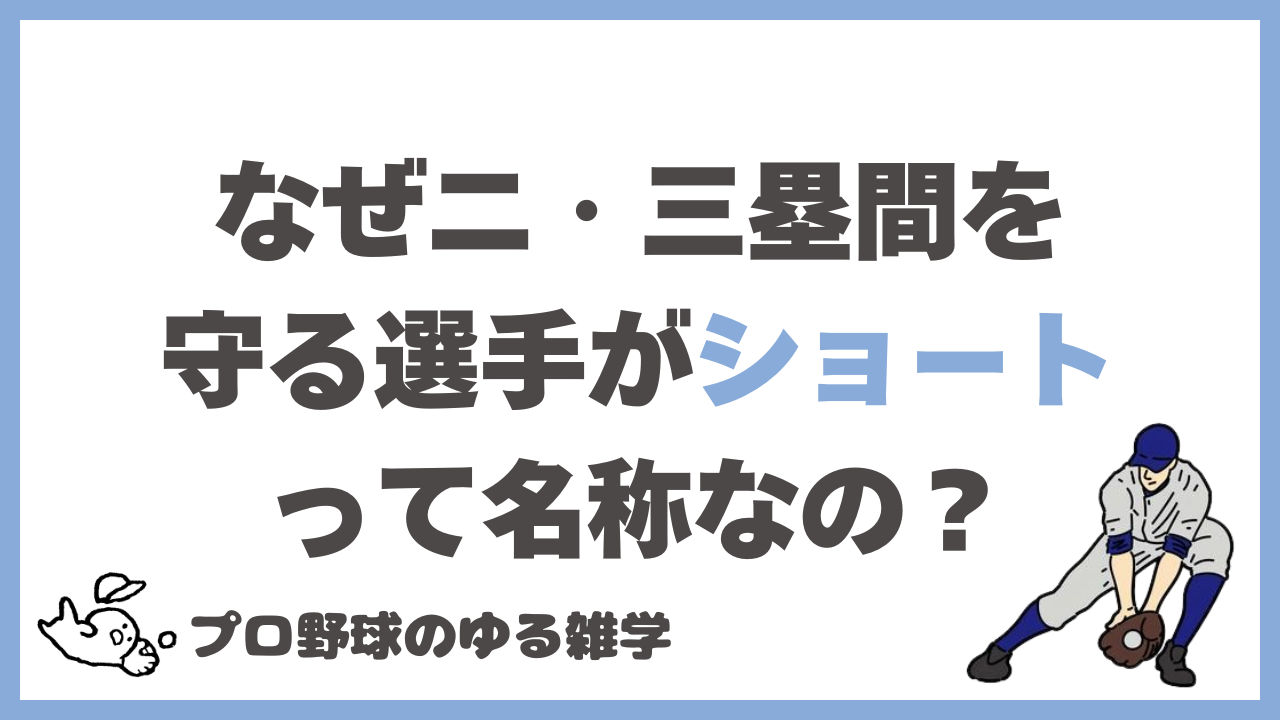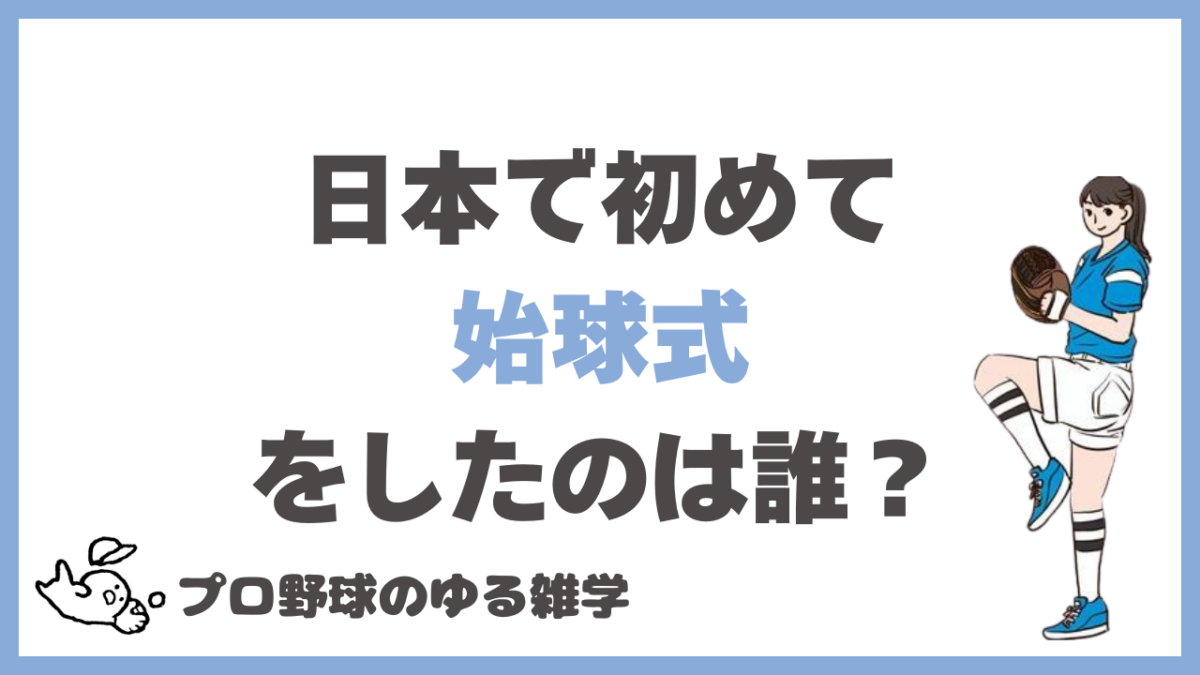野球には9つのポジションがあり、それぞれ分かりやすい名前がついています。
打者にボールを投げる人は「投手」、そのボールを受ける人は「捕手」、一塁付近を守る人は「一塁手」・・・というように、野球に詳しくない人でも、ポジション名を聞けばどの位置を守る人が想像できます。
しかし、二塁と三塁の間を守る人をショート(正式名称はショートストップ)と呼ぶことに、違和感はありませんか?
この記事では、なぜ二・三塁間を守るポジションを”ショート”と呼ぶのか、なぜ”遊撃手”と訳されたのかを解説します。
なぜ「ショート(ストップ)」となったのか?
アメリカで野球が始まった頃、実はショートストップは二人いたとのこと。
さらにショートのポジションは投手の左右に一人ずつ守っており、「短く、遮る」という意味で「ショート・ストップ」と名付けられたようです。
しかし投手付近に二人は不要では?という意見がでたため、ショートは一人となります。
次第にその一人は後ろに下がるようになり、二塁手の反対側を守るようになります。
より点を取られないように考えた結果、ショートは現在の守備位置となり、ショート(ショートストップ)という名称が残ったという訳です。
なぜ遊撃手と訳されたのか?
ショートストップを遊撃手と訳したのは、明治の教育者である中馬庚(ちゅうまかなえ)です。
明治時代の野球が伝わってまだ間もない頃には、正岡子規によって「short=短く」「stop=遮る」の直訳である「短遮」(たんしょ)と訳されました。
その後、中馬が「ショート・ストップは戦列で時期を見て待機し、動き回ってあちこちを固める「遊軍」のようだ」として、「遊撃手」という名称が定着しました。
「遊軍」とは、決まった任務につかず、必要に応じて活動できるよう待機している人のことであり、広い守備範囲を華麗に守るショートを指す言葉としてオシャレな訳ですね。
現在は遊撃手が定着し、違和感なく受け入れられるポジションだが、もし「短遮」(たんしょ)のまま現代になっていたらどうなっていたのか、個人的には気になるところです。

遊撃手って名付けはいいセンスですね。